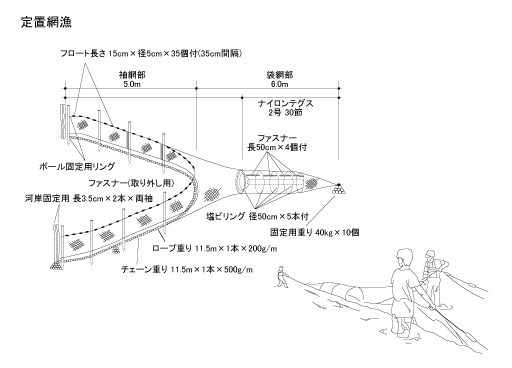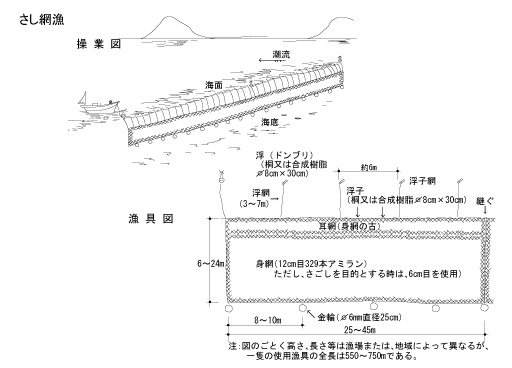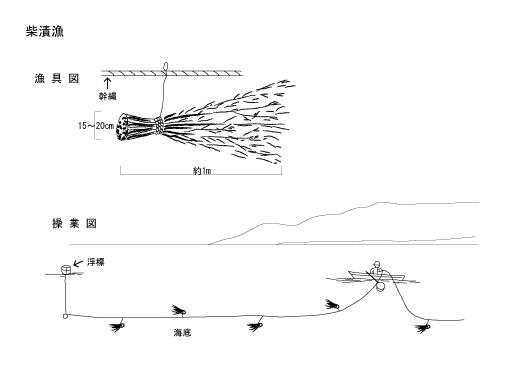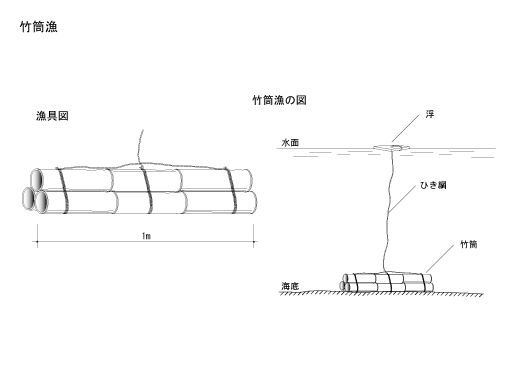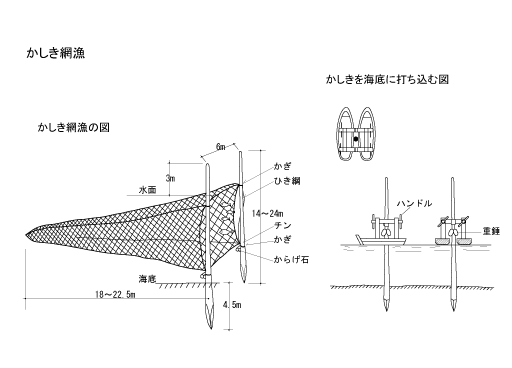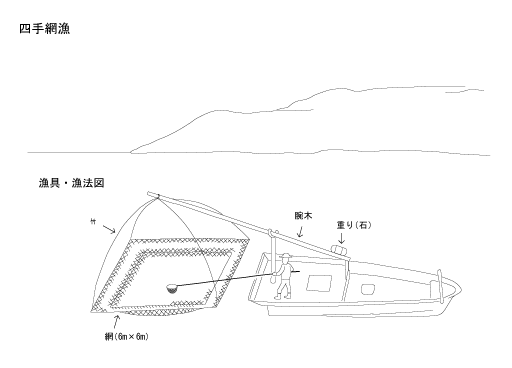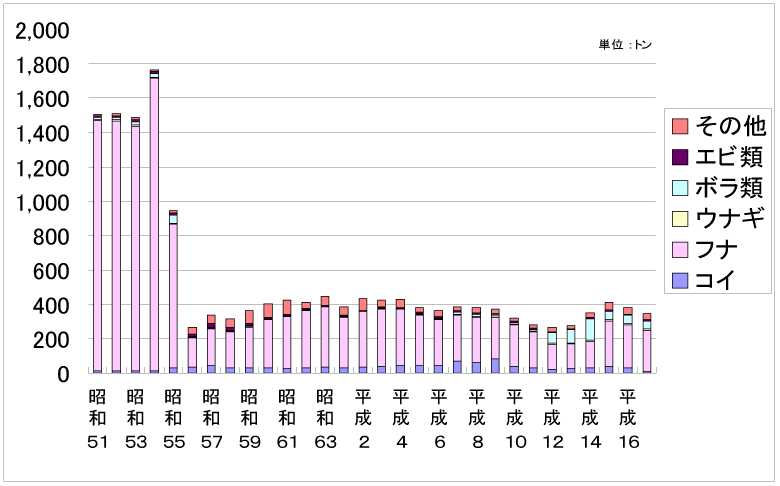児島湖では昔から漁業が盛んで、多様な漁法を駆使して漁業が営まれてきました。
そこで漁獲方法や漁獲量など、経年的な変化を様々な文献をもとに調べました。
【漁獲方法】 |
主な漁獲方法として、定置網漁、さし網漁、柴漬漁、竹筒漁等があります。
また児島湾独特のかしき網漁や観光漁業としての四手網漁があります。
詳細は以下に説明します。
参考文献
定置網漁は、「平成9年度版 河川水辺の国勢調査マニュアル[河川版] 建設省河川局河川環境課(1997)。
さし網漁、柴漬漁、かしき網漁、四手網漁は岡山文庫(89)「岡山の漁業」 昭和55年5月10日初版発行、著者:西川 太
「発行所:日本文教出版株式会社」を参考にしました。
竹筒漁はインターネットで検索し、写真を参考に製作しました。
|
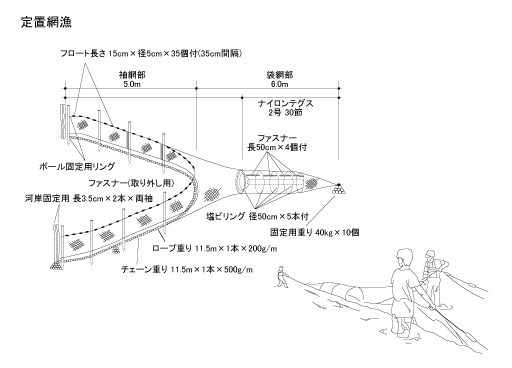 |
定置網漁
フナ、ウナギ、エビ、モロコなど
約6メートルの網に浮きと重しを上下端に付け、竹竿を立てて装着し、魚を誘導します。夕方に水中におろして、朝方に揚げます。
児島湖で最も主流な漁法のひとつです。
|
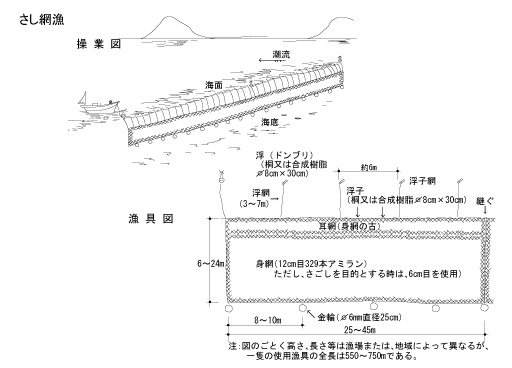 |
さし網漁
フナ、ウナギ、エビ、モロコなど
魚の群れを網で囲い、徐々に網を縮めて、魚を網目に刺させるか、魚を絡ませて採捕する仕組みです。
一般に使用されてるものは帯状で、下部には鉛や陶器の沈子が取り付けられ、網が垂直になるように仕立てられています。
|
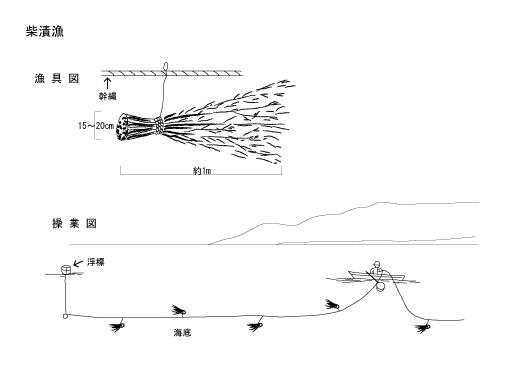 |
柴漬(しばづけ)漁
ウナギ、エビなど
名前からお漬物を連想してしまいますが、「柴漬漁」その昔は日本中で見られた漁法です。
雑木(ツツジ)の枝を1m位に切って、そして直径20cm程度の大きさに束ねた柴漬を沈めて魚がねぐらとして寄ってくるのを漁獲する方法です。
児島湖では、毎年3月中旬から約50束の柴漬を準備し、4月から漁を始めます。 |
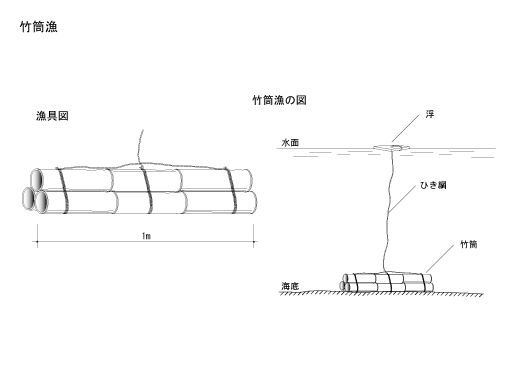 |
竹筒(スッポン)漁
ウナギ
その名のとおり、竹を使った漁法です。1mほどに裁断した竹を3本まとめて紐で縛り、ウナギを獲ります。ウナギが寝床として入り込んでくる習性を利用して獲ります。
児島湖の漁獲物の中でも、ウナギは市場で高く取引されています。 |
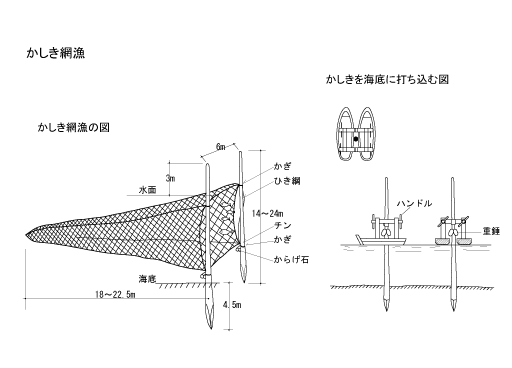 |
かしき網漁
シラウオ、アミ、ウナギ、エビ、ママカリなど
児島湾で古くから行われていた独特の漁法です。
何十人かで大きな船で柱を立てて、それに細長い網を張り、満ち潮時には、網の口を湾口に、引き潮時には、湾内に向けて張り、潮の流れにのってくる魚を捕獲します。昭和31年の児島湾の締切りによって、この漁業は操業できなくなりました。 |
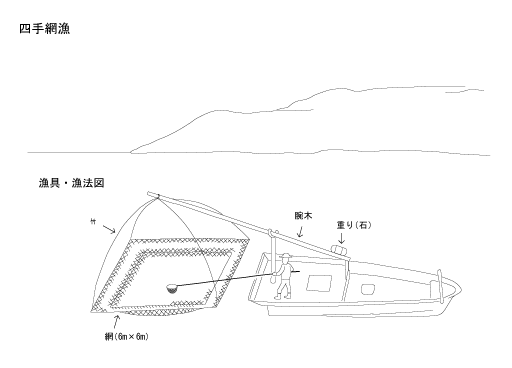 |
四手網漁
シラウオ、シラス、ウナギ、セイゴ、ベイカなど
正方形の網の四隅を竹の張力によって張り、腕木につけてぶら下げたもので、船の上からのものと陸上で小屋のものがあります。児島湖では、観光漁業として操業しています。 |
【漁獲状況】 |
児島湖では、現在主にフナ、ウナギ、エビ、モロコなどが漁獲されています。
近年は漁業従業者の高齢化や、消費者の需要の低下により、漁獲量は減少傾向にあります。 |
| 年度 | コイ | フナ | ウナギ | ボラ類 | エビ類 | その他 | 計 |
| 昭和51 |
12 |
1,459 |
6 |
11 |
10 |
7 |
1,505 |
| 昭和52 |
11 |
1,456 |
6 |
13 |
11 |
11 |
1,508 |
| 昭和53 |
12 |
1,425 |
6 |
17 |
13 |
14 |
1,487 |
| 昭和54 |
12 |
1,704 |
6 |
20 |
11 |
12 |
1,765 |
| 昭和55 |
30 |
838 |
3 |
48 |
12 |
15 |
946 |
| 昭和56 |
34 |
173 |
3 |
5 |
13 |
37 |
265 |
| 昭和57 |
44 |
214 |
3 |
7 |
19 |
49 |
336 |
| 昭和58 |
32 |
210 |
3 |
4 |
17 |
48 |
314 |
| 昭和59 |
31 |
238 |
3 |
4 |
15 |
73 |
364 |
| 昭和60 |
31 |
278 |
3 |
3 |
11 |
76 |
402 |
| 昭和61 |
27 |
301 |
3 |
2 |
9 |
82 |
424 |
| 昭和62 |
29 |
336 |
3 |
2 |
6 |
37 |
413 |
| 昭和63 |
34 |
350 |
2 |
1 |
5 |
56 |
448 |
| 平成元 |
32 |
294 |
2 |
3 |
4 |
48 |
383 |
| 平成2 |
35 |
322 |
2 |
2 |
4 |
68 |
433 |
| 平成3 |
38 |
336 |
2 |
3 |
6 |
41 |
426 |
| 平成4 |
42 |
328 |
2 |
3 |
7 |
45 |
427 |
| 平成5 |
43 |
294 |
5 |
4 |
9 |
27 |
382 |
| 平成6 |
45 |
266 |
6 |
4 |
8 |
36 |
364 |
| 平成7 |
70 |
266 |
6 |
13 |
7 |
24 |
385 |
| 平成8 |
63 |
259 |
6 |
15 |
7 |
31 |
381 |
| 平成9 |
85 |
240 |
6 |
12 |
4 |
24 |
371 |
| 平成10 |
38 |
240 |
5 |
12 |
6 |
19 |
319 |
| 平成11 |
32 |
210 |
4 |
10 |
6 |
17 |
279 |
| 平成12 |
20 |
147 |
6 |
63 |
6 |
24 |
267 |
| 平成13 |
28 |
143 |
6 |
75 |
6 |
17 |
275 |
| 平成14 |
30 |
153 |
9 |
125 |
7 |
26 |
351 |
| 平成15 |
40 |
260 |
9 |
50 |
9 |
45 |
413 |
| 平成16 |
30 |
250 |
9 |
46 |
8 |
39 |
381 |
| 平成17 |
9 |
240 |
9 |
46 |
7 |
34 |
345 |
※数値は四捨五入してあるため、計と内訳は一致しない場合があります。
|
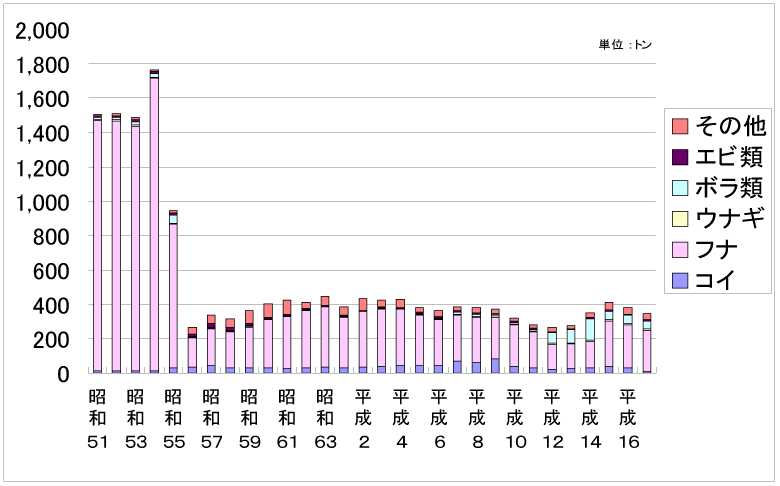 |
図 児島湖における漁獲状況変化
(農林水産省大臣官房統計部編集
「漁業・養殖業生産統計年報」より作成) |
【コラム】 |
春夏秋冬児島湖に、魚類調査のために舟で出ました。10月中旬に舟を走らせた時に、ボラたちが並泳してくれました。舟もスピードがありましたが、ボラたちも負けじと頑張っているようでした。舟の底に当たるボラがいたり、何匹かは、舟に飛び込んできたりしました。漁師さんたちは、「良いことが飛び込むぞ、」とげんをかつぐそうです。
ボラの成魚は水面を群れて泳いで、朝や夕方の時刻には水面を飛び跳ねます。ボラたちが飛び跳ねるには、いろいろな説がありますが、児島湖のボラの空を舞う勇姿を見ると、なぜか元気になれそうな気がします。
ボラのお話を2つほど書いてみようと思います。
ボラにはへそと呼ばれるところがあるのをご存知でしょうか。魚類なので、もちろん本当のへそではありません。胃の幽門部がへそのような形をしているのでへそと呼ばれています。ボラはエサを泥ごと食べるため、胃袋が頑丈にできていて、砂泥まじりのエサををうまく消化します。ニワトリのスナズリをやわらかくしたような歯ごたえで、珍味として喜ばれています。
ボラは、ブリやスズキのように出世魚です。ボラは、全国で親しまれている魚なので、呼び方もいろいろありますが、関西を例にあげてみます。「ハク」→「オボコ」→「スバシリ」→「イナ」→「ボラ」→「トド」という具合です。「とどのつまり」という言葉がありますが、この語源は「トド」がこれ以上は大きくならないことからきています。
|